
世帯年収600万円の共働き夫婦が住宅購入を検討する際、「いくら借りられるか」ばかりに目がいってしまう方も多いのではないでしょうか。
「借入可能額」と「無理なく返せる額」はまったく別物で、上限まで借りると将来的に家計が圧迫される恐れがあります。
今回は山形県南を中心にその他幅広いエリアで多くのご家族の家づくりをサポートしてきた工務店『ミナガワ建設』が、共働き夫婦ならではのローンの組み方や、失敗しない借入額の決め方についてわかりやすく解説します。
10年後、20年後もご家族みんなが笑顔でいられるように、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
世帯年収600万円の住宅ローン|借入額の目安
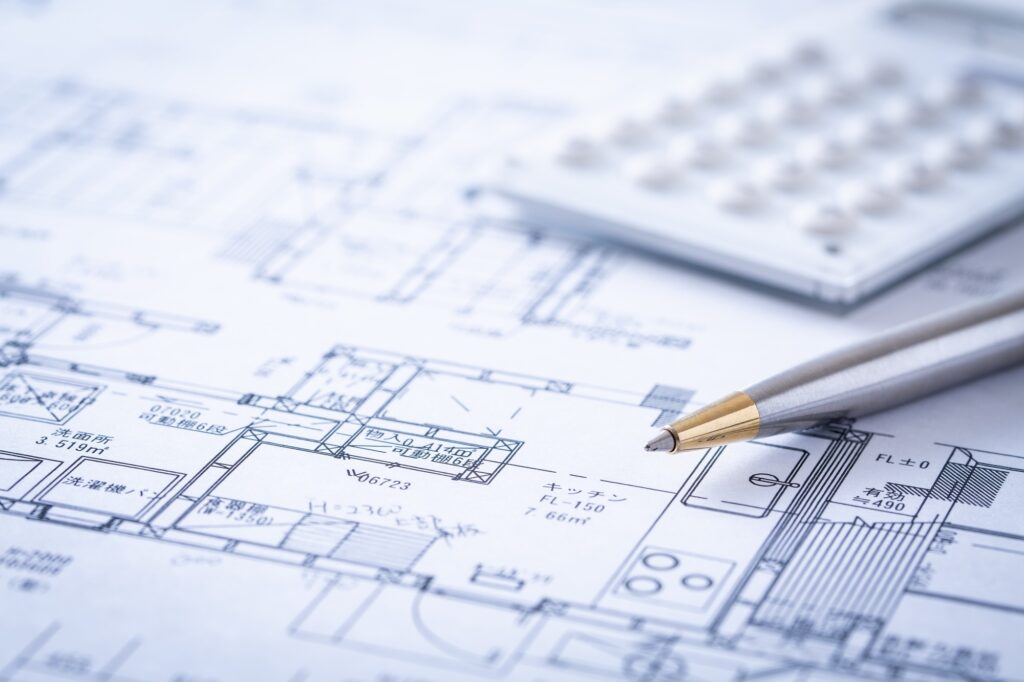
ここでは、借入額の目安と、見落としがちな「借入可能額」について解説します。
借入額の目安を決める2つの指標
住宅ローンの借入額は「年収倍率」と「返済負担率」2つの指標で考えます。
年収倍率:住宅購入費用が年収の何倍かを示す指標
一般的に、無理のない範囲は年収の5倍〜7倍とされています。
年収倍率 = 住宅の購入費用 ÷ 年収
世帯年収600万円の場合、借入額の目安は3,000万円〜4,200万円です。
ただし、これはあくまで目安であり、家族構成やライフスタイルによって適正な金額は異なります。
返済負担率:年収に占める年間返済額の割合
多くの金融機関は額面年収の30%〜35%を上限としますが、安心して生活するには「手取り年収」の20%〜25%に収めるのが理想です。
実際に使える「手取り」で計算するのが、家計を圧迫しないためのポイントです。
返済負担率 = 年間の返済総額 ÷ 年収 × 100
例えば、世帯年収600万円の手取り額を約480万円と仮定した場合、返済負担率20%であれば、年間の返済額は120万円(月々10万円)が目安です。
〈参考〉年収による借入額などの制限はありますか|住宅金融支援機構
「借入可能額」と「無理なく返せる額」はまったくの別物
金融機関が提示する「借入可能額」は、返済負担率の上限で計算されている場合が多く、世帯年収600万円なら5,000万円以上借りられるケースもあります。
「借りられる上限額」と「無理なく返せる額」は分けて考えましょう。
上限額まで借りると、毎月の返済で家計が圧迫され、教育費に充てることや貯蓄ができなくなるなどのリスクがあります。
金融機関の言葉は参考程度に、ご家庭のライフプランに合った「無理なく返せる額」を基準にすると安心です。
みんなが借りている住宅ローンの借入額・返済負担率の平均
他の方がどれくらい借りているのかも参考にしましょう。
住宅金融支援機構の「2023年度 フラット35利用者調査」によると、平均購入価格や年収倍率は以下の通りです。
| 住宅の種類 | 所要資金(全国平均) | 年収倍率(全国平均) |
|---|---|---|
| 土地付注文住宅 | 4,903万円 | 7.6倍 |
| 注文住宅(土地除く) | 3,863万円 | 7.0倍 |
| 建売住宅 | 3,603万円 | 6.6倍 |
〈引用〉2023年度 フラット35利用者調査|住宅金融支援機構
年収倍率の平均は6.6倍〜7.6倍と高い水準ですが、これは住宅価格の高騰や低金利が背景にあると考えられます。
年収倍率のデータを参考にしつつも、ご家庭の家計と照らし合わせて慎重に判断しましょう。
共働き夫婦の住宅ローンの3つの組み方|メリット・デメリット

共働き夫婦の住宅ローンは、ご夫婦の働き方やライフプランによって適した方法が異なります。
代表的な3つの方法を解説します。
単独ローン|パートナーの収入に不安がある・手続きをシンプルにしたい
夫または妻のどちらか一方が単独で住宅ローンを契約する方法です。
最もシンプルな契約形態で、パートナーには返済義務が生じません。
| こんな人におすすめ |
・パートナーの収入に頼らず、一人で返済計画を立てたい
・手続きをシンプルに済ませたい
・パートナーが将来、別のローンを組む可能性がある
|
| メリット |
・手続きがシンプル
・パートナーに返済義務がない
・パートナーの信用情報に影響されない
・ローンを組んでいないパートナーの柔軟性が高い
|
| デメリット |
・借入可能額が少なくなる
|
ペアローン|ローン控除を最大化したい・対等な関係を重視する
ご夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約する方法です。
お互いがパートナーのローンの連帯保証人になります。
| こんな人におすすめ |
・夫婦ともに安定した収入があり、住宅ローン控除のメリットを最大化したい
・借入希望額が高額で、一人では届かない
・パートナーを尊重し、対等な立場で家を持ちたい
|
| メリット |
・借入可能額を大きく増やせる
・節税効果が最も高い
・それぞれが団信に加入できる
|
| デメリット |
・諸費用が2倍かかる
・パートナーに不幸があっても、残された方の返済義務は残る ・契約が2本あり、それぞれに手続きが必要 ・離婚時の手続きが複雑 |
働き方はご家庭によってさまざまで、「夫は正社員、妻はパート」といったケースでは、ローンの組み方や注意点も異なってきます。
ご自身の働き方に合ったローンの組み方について、詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
〈関連ページ〉"夫正社員・妻パート"でも住宅ローンは組めるのか?組み方別のメリット・デメリットや選び方、注意点も解説
収入合算|単独では希望額に届かないけど手続きはシンプルにしたい
ご夫婦の収入を合算して一つの住宅ローンを契約する方法です。
「連帯債務」と「連帯保証」の2タイプがあり、以下の場合におすすめです。
- 単独では希望額に届かないが、手続きはシンプルにしたい
- パートナーがパートや契約社員で、単独ローンを組むのが難しい
連帯債務
ご夫婦が二人で一つのローンに同等の返済義務を負う契約です。
持分割合に応じて二人とも住宅ローン控除を受けられますが、団信は基本的に主債務者しか加入できません。
| メリット |
・二人とも住宅ローン控除を受けられる
・単独ローンより借入可能額を増やせる ・諸費用は1本分で済む ・「夫婦連生団信」を選べる場合がある |
| デメリット |
・二人とも同等の返済義務を負う
・団信に加入できないリスクがある ・借り換え先の選択肢が少ない
|
連帯保証
一方が主債務者、パートナーが連帯保証人となる契約です。
住宅ローン控除や団信の対象は主債務者のみとなり、連帯保証人は返済義務を負うにもかかわらず控除を受けられません。
| メリット |
・単独ローンより借入可能額を増やせる
・諸費用は1本分で済む ・パートナーの収入が少なくても合算できる場合がある |
| デメリット |
・連帯保証人の負担が大きい
・主債務者が返済不能になると全額返済義務を負う ・連帯保証人自身のローン審査に影響する |
世帯年収600万円で失敗しない住宅ローンのポイント3選
ここでは、住宅ローンで失敗しないためのポイントを3つ解説します。
ライフプランニングを立てる

住宅ローンは長期にわたる契約のため、今の家計状況だけで返済計画を立てるのは危険です。
将来のライフイベントと、それに伴う支出・収入の変化についても、あらかじめ見通しを立てておきましょう。
- 産休・育休による収入減:育児休業中や時短勤務からの復帰後は世帯収入が減少します。
- 想定以上の支出:お子さまの教育費や、家の固定資産税、将来の修繕費など、見えにくいコストも計画に入れておく必要があります。
- 昇給の不確実性:「将来は昇給するはず」という楽観的な見通しは避け、現在の収入をベースに計画を立てると安心です。
資金計画では、月々のローン返済だけでなく、光熱費などのランニングコストも考慮することが大切です。
最近では、ランニングコストの削減や省エネ住宅向けの補助金活用を見据えて、太陽光発電システムの導入を検討するご家庭も増えています。
雪国で太陽光発電を設置するメリットついて、以下の記事で解説しています。
〈関連ページ〉太陽光発電は雪国でも可能|理由やメリット・デメリット、雪下ろしが不要な理由について解説
金利タイプの選び方
金利タイプは「目先の支払い」か、「未来の安心」のどちらを重視するか、価値観やライフプランに合わせて、タイプを選びましょう。
- 変動金利:当初の金利が低いですが、将来金利が上昇すると返済額が増えるリスクがある。金利上昇に対応できる家計の余裕がある人向け。
- 固定金利:返済額が借入期間中ずっと変わらないため、計画が立てやすく安心。将来の金利変動に不安を感じたくない人に向いている。
住宅ローン審査で重視されるポイント

住宅ローン審査のマイナス評価につながる要素は、事前に解消しておきましょう。
【住宅ローン審査前のチェックリスト】
- 支払遅延はないか:スマホ代やカードの支払遅延は個人信用情報に記録されます。
- 他の借入はないか:カードローンやリボ払いは完済しておきましょう。
- 勤続年数は1年以上か:多くの金融機関で勤続1年以上が条件です。
- 健康状態は良好か:団信に加入できないとローンが組めない場合があります。
山形県南を中心にその他幅広いエリアで注文住宅をご検討の方は、ぜひ一度ミナガワ建設へご相談ください。
お客様一人ひとりのライフプランや、無理のない資金計画に寄り添いながら、高性能な住まいのご提案、各種補助金の活用まで、後悔しない理想の家づくりをトータルでサポートいたします。
住宅ローンの頭金の目安|フルローンのリスク

「頭金」をいくら用意するか、また「フルローン」でも大丈夫なのかは多くの人が悩む点です。
ここでは、頭金の目安とフルローンについて解説します。
頭金の目安は「物件価格の1〜2割」
一般的に、頭金は物件価格の1割〜2割が目安です。
頭金を用意すると、借入額が減って毎月の返済が楽になり、審査にも通りやすくなるメリットがあります。
頭金を貯めている間の家賃発生や、金利・物件価格が上昇するリスクも考慮し、タイミングを判断しましょう。
フルローンは「売ってもローンが残る」場合がある
フルローンは頭金なしで家を買えるメリットがありますが、住宅の資産価値がローン残高を下回る「担保割れ」のリスクが高まります。
この状態で家を売却すると、売却代金だけではローンを完済できず、「家はないのに借金だけが残る」という事態になりかねません。
活用したい税制度と補助金

税金の控除や補助金などの制度は、知っているか知らないかで100万円単位の差が生まれる場合もあります。
ここでは、必ず押さえておきたい代表的な制度をご紹介します。
住宅ローン控除|共働き夫婦は「組み方」で控除額が変わる
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%を最大13年間、税金から控除できる制度です。
共働き夫婦の場合、ローンの組み方によって世帯全体の控除額が変わるため、どの方法が有利か事前に確認しましょう。
申請しないともらえない補助金・助成金
国や自治体には、省エネ住宅や子育て世帯を支援する補助金制度があります。
住宅の購入を計画する段階で、ハウスメーカーや工務店の担当者への相談や、自治体のホームページを確認し、利用できる制度がないか必ずチェックしましょう。
ミナガワ建設が拠点とする山形県で利用できる最新の補助金制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
〈関連ページ〉山形県の住宅補助金申請の流れ|2025年最新情報、申請期限も解説
山形県南を中心にその他幅広いエリアで注文住宅をご検討の方は、ぜひ一度ミナガワ建設へご相談ください。
ご家族の夢を形にするだけでなく、税制度や補助金を最大限に活用し、資金面でもご満足いただける家づくりをご提案します。
まとめ
世帯年収600万円の共働き夫婦が住宅ローンで後悔しないために、「借りられる額」ではなく「無理なく返せる額」を基準に考えることが何よりも大切です。
まずご家庭のライフプランを明確にし、長期的な視点で資金計画を立てましょう。
この記事が、理想の住まいづくりに少しでもお役立ていただければ幸いです。
